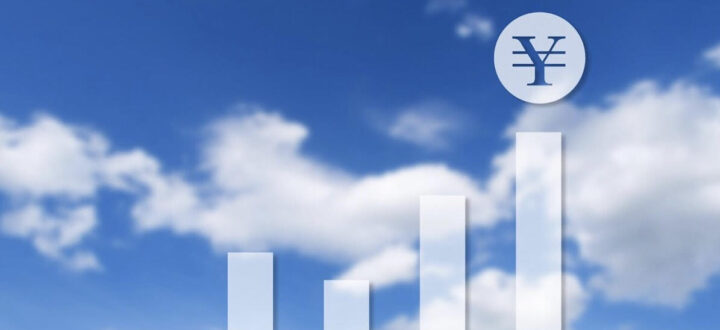【2024年最新】経営コンサルタントとは|仕事内容や資格・必要なスキルを解説!
Post Date:
2023-08-02 / Update-date:
2024-06-29 /
Category:
戦略コンサル特集

経営コンサルタントとは、経営に関するアドバイスや戦略策定を行う専門家のことです。その仕事内容や魅力、未経験からの転職に必要なスキル、さらにキャリアパスについて詳しく紹介します。
- 経営コンサルタントとは
- 経営コンサルタントの主な仕事内容
- 各職位における経営コンサルタントの仕事内容
- 経営コンサルタントのやりがいや魅力
- 経営コンサルタントに向いている人の特徴
- 経営コンサルタントの年収相場
- 未経験から経営コンサルタントになることはできるのか
- 未経験から経営コンサルタントになるために必要な経験
- 未経験から経営コンサルタントになるために必要なスキル
- 未経験から経営コンサルタントになるためにおすすめの資格
- 経営コンサルタントは将来性がある仕事なのか
- 経営コンサルタントのキャリアパス
経営コンサルタントとは
コンサルタントはクライアントの抱える課題を見つけ、その解決策を提案・実行・支援することを業務の中心としています。各コンサルタントは専門分野を持っており、企業の事業計画や新規事業の提案を行う戦略コンサルタント、ITと経営を結びつけ、IT戦略やDX推進を行うITコンサルタント、人事制度、組織制度に関する課題を専門とする組織・人事コンサルタント、M&A(合併・買収)に関わる経営戦略の決定から相手企業との契約締結までの様々なコンサルティングを行うFAS、などが一例となります。
経営コンサルタントに明確な定義はないのですが、上述したような様々な分野を包括し、総合的に経営課題に関する提案・支援するコンサルタントのことを指します。
かつては狭き門と思われていたコンサル業界ですが、コンサルタントの認知の高まりや、21世紀になり経営環境の変化スピードがさらに加速したことで業界自体が拡大し、未経験人材の採用も活発化しており、経営コンサルタントの場合も同様に未経験からの採用も大きなレンジをしめています。
戦略コンサルタントとの違い
経営コンサルタントと戦略コンサルタントは、いくつかの点で違いがあります。経営コンサルタントは、人事や管理職など経営に関連する問題点を幅広く分析し、解決策を提案します。一方で、戦略コンサルタントは、企業が競争に勝つための経営戦略を提案する専門家とされています。
経営コンサルタントはクライアントの経営問題を把握し、幅広い分析を行い解決策を出す一方、戦略コンサルタントは企業の方針や戦略を中心に考えています。
また、戦略コンサルタントについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
▶戦略コンサルタントとは?具体的な仕事内容や必要なスキル・年収ついて解説!
経営コンサルタントの主な仕事内容
経営コンサルは具体的なデータや論理的思考力を用いてクライアントの企業問題を解決する経営の専門家で、企業の経営計画や事業戦略立案を通じて激しい競争の中での業績向上を目指します。経営者と直接向き合い経営支援を行う立場から常日ごろから業界知識/IT最新スキル/法規制・改正の動きをキャッチアップする必要があります。
経営コンサルの仕事内容は案件やポジションによっても多少異なってきますが、企業の抱える問題の根幹をデータや社内インタビュー等を元に洗い出し、検証・分析することから始まり、その後、解決策の立案や実行支援を行います。時にはクライアントの利益のために現場や経営陣と向き合いながら説得を必要とする場面も少なくありません。
また、クライアントの企業規模によっても求められる役割は異なり、中小企業相手の場合は相談役として税務/法務から人事・営業に至るまで、様々な問題を経営者と二人三脚で歩んでいくことが求められます。企業規模が大きい場合、案件にもチームであたり、かつ案件内容もより具体的で現場に近いことが多く、成果を出すということがより重要になる傾向があります。
各職位における経営コンサルタントの仕事内容
経営コンサルタントは各職位において仕事内容が異なります。本章では、各職位における経営コンサルタントの仕事内容について解説いたします。
マネージャー
プロジェクトの指揮監督の責任者として予算管理とクライアントとの折衝までを担当するため、コンサルタントの能力に加え、高いマネジメント能力も求められる職位になります。また管理職として人材の育成や採用など、全社的な取り組みを担当することにもなります。
リーダーとして、プロジェクトをマネジメントし、全体のアウトプットに責任を持ち、クライアントの担当者との信頼関係構築、意見の折衝、プロジェクトメンバーの業務内容の管理や指導などを行います。またファームによっては一定の売上の獲得を求められ、営業スキルが求められるケースもあります。
コンサルタント
マネージャーの指揮下において、自ら情報を収集・分析し提言を行い、一定領域の作業責任者としてアナリストと協業しながら成果物を作成することになります。
プロジェクトにて一定の範囲の責任を持ち、自分のチームのアウトプットにコミットする職位です。新卒では入社後3〜5年程度の経験、中途採用の場合は5年程度の経験を有するものを想定しています。クライアントとの折衝やプロジェクトにおけるリード等の経験を徐々に積んでいくことでマネージャーへの昇進を目指します。クライアント担当者との信頼構築、後輩やアナリストの指導といった管理職に必要なスキルを身につける段階でもあります。
アナリスト
作業担当者として、各種リサーチや資料作成を行う職位になります。
プロジェクトメンバーとして、プロジェクトに参画し、担当する業務・作業の遂行を遂行します。主に新卒、第2新卒メンバーが入社後、本職位からスタートします。リサーチ業務、議事録作成などの業務を通じて、コンサルタントに必要な仮説思考や論理的思考力といった基礎的なスキルを身につけてゆくのです。地道な業務が多いながら、多くの資料と向き合うアナリストだからこその「発見」があり、それがプロジェクトの機動力となるため、チームにとっても重要なポジションだと言えるでしょう。
経営コンサルタントのやりがいや魅力
経営コンサルタントは、多くのやりがいや魅力があります。本章では、経営コンサルタントの主な魅力とやりがいを3つ紹介させていただきます。
課題の難易度が高く達成感を感じやすい
経営コンサルタントの魅力の一つは、直面する課題の難易度が高いことです。企業から依頼を受けて経営上の問題点を分析し、原因を究明して解決策を見つけていくため、複雑な課題に対峙することが多いです。これにより、普段の業務に比べて知的な刺激が強く、課題をクリアした時に達成感を感じやすい環境が整っています。
知的好奇心を満たしやすい
経営コンサルタントのもう一つの魅力は、知的好奇心を満たしやすい環境であることです。戦略コンサルタントは、様々な領域にわたる複合的な課題を扱うことが多く、一つのプロジェクト内でも様々な領域の知見を学べるため、知的な探究心を満たすことができます。この環境で働くことで、自身のスキルや知識を向上させながら、クライアント企業の問題を解決する喜びを感じることができるでしょう。
優秀な人と働けスキルを向上させやすい
経営コンサルタントの環境では、優秀な人々と共に仕事をする機会が増えるため、スキルアップが期待できます。コンサルティングファームは多くのトップエリートが集まる場所であり、そのような環境で働くことで高いレベルのスキルを持つ同僚から学び、自らの能力を高めることができるでしょう。また、経営コンサルタントの仕事はプロジェクトごとに異なるため、様々な経験を積むことができるのも特徴です。これらの要素が自己成長につながり、キャリアの発展にも繋がるでしょう。
経営コンサルタントの魅力は、高度な課題に挑戦することで得られる達成感、知的好奇心を刺激される環境、そして優秀な人々との共同作業によるスキルアップの機会にあります。これらの要素が、多くの人々を経営コンサルタントの職業へと魅了しています。
経営コンサルタントに向いている人の特徴
経営コンサルタントに向いている方の特徴は、下記の6つの特徴があります。1つ1つ解説していきます。
クライアントファーストで動ける方
コンサルタントの仕事の本質はクライアントの成功のサポートにあります。そのため、クライアントが納得し、結果に満足するということが最終的な目標となります。「自分がこうしたい」という感情より先に「クライアントの方はこうしたいだろう」という思考が出来る方はコンサルタントに向いていると言えます。もちろん「自分がこうしたい」がクライアント視点でも正しく、明確に進むべき方向性/施策であればそれに越したことはありませんが、その場合はクライアントの状況や人間関係を踏まえて、相手を納得させる必要があります。「正しいからやる」ではなく、「正しいと腹落ちして、動いてもらうこと」が真のクライアントファーストでしょう。
また、あくまでクライアントが主役ですので、黒子役に徹することになります。プロジェクトの成功が新聞等に取り上げられる際にも、コンサルタントの貢献が取り上げられることはほぼありません。ただ、表向きで目立たなくても、クライアントの成果やプロジェクトの世の中へのインパクトを密かに喜べる方が向いているでしょう。
論理的思考が出来る方
こちらはよく聞くワードかもしれません。近年では『●●流論理的思考法』といった本も多く出版されており、「コンサル=論理的、ロジック、ロジカル」という印象は世の中一般で浸透しているでしょう。
では論理的思考とは具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。基本的には、『「根拠」→「結論」』という道筋が立っていることが重要となります。しかし、それだけでは十分とは言えません。その他のロジックを追求する視点として、コンサルティング業界では「MECE」であることが重要となります。MECEとは「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字であり、要するに「もれなく、ダブりなく」ということを意味しています。明確な答えのない課題を解決するコンサルタントは、単に論理の筋道が通っているだけでなく、あらゆる事柄を検討した上で最も論理の筋道が通っているものを提示する必要があります。
勿論、全ての検討がロジックのみで進むわけではありませんし、時に右脳的な発想や、相手の気持ちを踏まえた上での判断もありますし、発想から出てきた仮説が結果的に最も良い答えであることもあります。ただし、その際でも、相手への説明や、本当にその仮説が正しいかの検証の際には、論理的なプロセスを踏むことになりますので、やはり「論理的思考」はコンサルタントの最低限の素養と言えます。
仕事の速い方
コンサルタントの仕事は、とにかく速さが要求されます。コンサルタントがアサインされるプロジェクトは3か月~6か月ほどのものが多く、その中で情報収集、分析、仮説の構築・検証を行い、さらには実行の支援も求められるものがあります。当然、実行には時間がかかりますから、その前段階で時間を使いすぎてはいけません。とにかく素早く解決にむけた施策を考え出さなければならず、また短い期間の中で資料の質も期待されているため、日々の時間の使い方の見直しや軌道修正、作業面では前手での取り組みや短時間で処理するためのスキル、単純作業の外部活用等が必要になります。
つまり自身の作業のスピードを上げるのみならず、うまく段取りをして外部を使い、必要な期限までに最高のアウトプットを出す、仕事の進め方を身につけなければなりません。
クライアント/チームメンバーと良い人間関係が築ける方
クライアントに解決策を実行してもらうためには、論理的な思考だけでなく、クライアントに信頼してもらうことが不可欠となります。クライアントに真摯に向き合い、自分事のように課題解決を行うという姿勢で仕事をすることが大切です。
また、コンサルタントは基本的にプロジェクト毎にチームが編成されます。チーム編成の際には、関わったことのない方とプロジェクトを遂行することもあります。そうした中で、自らの役割を認識し、チームメンバーと互いに信頼感のあるリレーションを構築したうえで、連携していく必要があります。
成長意欲のある方
コンサルタントとして仕事をしていると、次々に知らないことやできないことが出てきます。しかし、コンサルタントに対して非常に高いフィーを支払っているクライアントの前で「知らないのでできません」と言うわけにはいけません。もし知らない/できないことがあれば、次の日までにキャッチアップするくらいの気概のある方、また、そのキャッチアップを知的好奇心から楽しむことが出来る方がコンサルタントに向いていると言えるでしょう。
また、コンサルタントはその職位によって求められるスキルセット・マインドセットが異なります。コンサルティングファームによっては研修制度が用意されているので、それらを活用して自ら学んでいくことに加え、その求められるスキル/マインドセットのために、これまでの考え方や仕事のプロセスについて、一部アップデートしていくことをいとわないマインドがコンサルタントには不可欠です。
厳しい状況をポジティブに乗り越えられる方
コンサルタントは求められる能力が高く、仕事量やクライアントからの高いレベルでのプレッシャーを受ける職業です。また、社内外問わず複雑な人間関係の渦中に置かれることもしばしばあります。肉体的・知能的・精神的ストレスにさらされる中で、その状況を成長という視点でポジティブに乗り越えられる方が向いております。
また、経営コンサルタントに向いている人について詳しく知りたいという方は、下記の記事を参考にしてください。
▶経営コンサルタントに向いている人の特徴を紹介。おすすめの資格やスキルも解説
経営コンサルタントの年収相場
コンサルタントの年収は、経験や企業によって大きく異なりますので一概に言う事は出来ません。しかし、高いスキルと知見を持って成果を出し続ける仕事である分、その見返りとしての給与は高水準である場合が多いです。コンサルファームに入社して5年程度で1000万円を超えることも少なくなく、マネージャーになると2000万円を目指すこともできます。
ただし、コンサルタントに転職したての際には一時的に給与が下がってしまうケースもあるので、高い給与を求めるという動機のみで転職を目指す場合には注意が必要です。一般的には事業会社比較で年収は高いため、もし転職時に下がる場合があったとしても昇進すれば現年収を大きく超える場合がほとんどでしょう。
コンサルへの転職を目指す際に年収は魅力の1つですが、それのみに執着してしまうと仕事内容や環境に不満を抱えてしまう場合も少なくありません。自分が仕事に求めているものに優先順位をつけ、バランス感を持って企業選びをする必要があります。
| 役職 | 年齢 | 給与 | コンサル歴 |
| アナリスト | 22~28歳 | 400万~700万円 | 0~3年 |
| コンサルタント | 25~35歳 | 700万~900万円 | 0~6年 |
| マネージャー | 30歳~ | 900万~1400万円 | 2~10年 |
| シニアマネージャー | 35歳~ | 1300万~1800万円 | 5~15年 |
| パートナー | 実績による | 2000万円~ | 7年以上 |
未経験から経営コンサルタントになることはできるのか
コンサルファームでは新卒や第二新卒などのポテンシャル採用も行っていますが、基本的には前職でのスキルやノウハウを生かして活躍してほしいと考えている場合も多く、中途採用に力を入れています。それぞれのファームやポジションによって力を入れている分野やポジションの業務内容、求人要件は違っていますので自分の経験に合うポジションを見つけ出すことが重要だと言えます。その際、インターネットで調べるだけでなく、セミナーへの参加や転職エージェントと面談する等、生の情報を収集することも大切になります。
以下の記事ではより具体的に未経験でのコンサル転職についてポイントや対策方法をまとめています。
未経験から経営コンサルタントになるために必要な経験
経営コンサルタントとしてのキャリアを築くためには、未経験からでもいくつかの重要な経験が求められます。以下に必要な経験をまとめます。
- 資格や専門性の習得:経営コンサルタントとしての資格や専門的な知識を習得することが重要です。例として、MBA(経営学修士)や公認会計士の資格などが挙げられます。これらの資格は、経営コンサルタントとしての基礎的なスキルや知識を身に付けるために役立ちます。
- 英語力の向上: 経営コンサルティングファームでは、グローバルな案件に携わることが多いため、英語力の向上が必要です。国際的なクライアントとのコミュニケーションや報告書の作成などで役立ちます。
- キャリアやスキルの構築: 経営コンサルタントとしての経験やスキルが求められます。そのため、他の業界での経験を積むことや、プロジェクトマネジメントなどのスキルを身に付けることが重要です。また、30歳前半までに経験を積むことが、コンサルタント業界において有利に働く場合もあります。
未経験から経営コンサルタントとしての道を歩むためには、資格や専門性の習得、英語力の向上、そしてキャリアやスキルの構築が必要です。これらの要素を準備することで、経営コンサルティングの世界で活躍するチャンスを高めることができるでしょう。
未経験から経営コンサルタントになるために必要なスキル
コンサルファームは事業会社とは違いコンサルタント個人の思考力と専門知識を商品としているため、高いスキルを求められる環境にあります。一方で、転職の時点ではコンサルタントとしての経験を求めるというよりは未経験であってもコンサルタントとしての基礎能力、資質を見るポテンシャルを評価し採用を行っています。以下では、コンサルタントの基礎能力、ポテンシャルの一例として論理的思考力、ヒアリング能力、経営学や法律等の専門知識、コミュニケーション能力について解説します。
論理的思考力
コンサルタントに必要なスキルはいくつかありますが、全てのコンサルタントに共通して求められる最も重要なスキルのうちの一つは論理的思考力です。業界で何十年の経験をもつ経営者と向き合う中で、コンサルタントは論理的な思考力を武器に価値を提供しています。この能力はコンサルタントがプロジェクトを進めるにあたり、課題の特定、情報収集、問題解決案の策定などすべての業務の基礎となるスキルで、経営コンサルとして論理的思考を活かし、0ベースで仮説を積み上げていくことでクライアントの課題の解決の支援を行っています。
ヒアリング能力
コンサルタントの業務はプロジェクトワークが中心になるため、毎回クライアントごとに、インタビューを行い各企業の状況を把握し、クライアントごとに異なる経営課題や解決策を見つけ出す必要があります。ヒアリング力といっても単にクライアントから話を上手く聞く能力を示しているのではなく、企業の抱えている経営的な本質的問題を見つけ出すリサーチ力、分析力のことを指し、高いヒアリング力を保つためには論理的な思考力やコミュニケーション能力を総動員する必要があります。
経営学や法律等の専門知識
経営コンサルタントは企業の経営問題に多角的に向き合う必要があるために、クライアントの企業知識や業界知識だけではなく経営、法律やIT、人事といった様々な知識を持っている必要があります。また、企業の経営環境の変化や技術革新が目まぐるしい現在においては、様々な最新情報を常にキャッチアップし続ける必要があるでしょう。一方で企業にまつわる全ての情報を理解することは非常に難しく、コンサルタントに求められる役割は、多くの情報・知識を「持っている」ことよりも、新しい知識をどのように吸収していくのかや、その知識をどうクライアントの現状に応用していくのかという点に重点があるとも言えます。
コミュニケーション能力
コンサルファームのプロジェクトではクライアント企業の社員やプロジェクトチームの様々な専門分野を持つメンバーなどの多くの関係者が存在し、その中で(案件によっては短期間に)共同作業を行うことが求められます。バックグランドが異なる様々なメンバーと、共通のゴールに向かって一緒にプロジェクトを行っていくためには、高いコミュニケーション能力が必要です。コミュニケーション能力といっても世間でいうような「話すことが上手い」というようなレベルではなく、論理的な思考に根差し自分の意図を100%正確に伝え、相手の話を100%正確に理解する能力という意味になります。
未経験から経営コンサルタントになるためにおすすめの資格
経営コンサルタントを目指すためには、特定の資格を取得することが有益です。以下に、未経験から経営コンサルタントになる際におすすめの資格を紹介します。
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営改善や問題解決のプロフェッショナルとしての資格です。経営コンサルティングの現場で重要なスキルや知識を身に付けることができます。また、中小企業に特化したコンサルティングを行いたい場合に役立つ資格となります。
税理士
税理士の資格は、税務や財務分野における専門家としての資格です。経営コンサルタントは、企業の税務や財務に関するアドバイスを行うことがあります。税理士の知識を持つことで、クライアントにより総合的なサポートができるでしょう。
公認会計士
公認会計士は、企業の経理や会計に関する専門家の資格です。経営コンサルタントがクライアントの業績や財務状況を分析し、戦略立案に活用する際に役立ちます。企業の財務データを理解する力は、経営コンサルティングにおいて重要な要素となります。
経営士
経営士は、経営戦略や組織運営に関する専門的な知識を持つ資格です。経営コンサルタントが経営戦略の策定や改善提案を行う際に役立ちます。経営士の資格を取得することで、より高度なコンサルティングが可能になるでしょう。
社会保険労務士
社会保険労務士は、労務管理や社会保険に関する専門家の資格です。人事管理や労務関連のアドバイスを行う場合に有用です。経営コンサルタントは、クライアントの人事制度や労務問題に対しても的確なアドバイスを提供する必要があります。
これらの資格を取得することで、経営コンサルタントとしてのスキルや専門性が高まり、クライアントに対してより信頼性のあるコンサルティングを行うことができるでしょう。ただし、経験やスキルも重要な要素ですので、資格取得と並行して経験を積むことも大切です。未経験からでもコンサルタントを目指すことは可能ですが、学び続ける姿勢と情熱が必要とされる職業であることを忘れずに取り組むことが重要です。
また、経営コンサルタントにおすすめの資格ついて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
▶経営コンサルタントにおすすめの資格7選|専門分野ごとに分けて解説!
経営コンサルタントは将来性がある仕事なのか
経営コンサルタントの将来性については、現在の状況や職業のトレンドを考慮する必要があります。AIやテクノロジーの進化により、一部の職業が置き換えられる可能性もある中で、コンサルタントの将来性を考察してみましょう。
世間一般にはコンサルタントのニーズは今後も続くと予想されています。特に顧客が求めるソリューションの範囲が拡大し、テクノロジーの進化やコンサルタントの一般化が進む中で、AIなどのITや顧客の社内にいるコンサル経験者に代替されない専門性の高いコンサルタントが求められています。そのため、情報のアップデートや幅広い知識とスキルが求められるでしょう。
また、日本では中小企業が企業全体のほとんどを占めており、これらの企業は課題を抱えていることが多いとされています。そのため、中小企業の活性化にコンサルタントが大きな期待を受けており、経営コンサルタントが活躍する機会は豊富だと考えられています。特にグローバル化やICTの進歩に伴い、海外展開や最新の技術導入のサポートが増えていることも、コンサルタントの需要を高める要因となっています。
総じて、経営コンサルタントの将来性は依然として高く、専門的な知識とスキルを持つコンサルタントの需要が続くと予想されます。ただし、テクノロジーや社会の変化に対応するために、常に情報を更新し専門性を高める努力が求められる職業であることを忘れずに、キャリアプランを考えることが重要です。
経営コンサルタントのキャリアパス
新卒や20代などのポテンシャル採用の場合はアナリストからキャリアを始め2年から5年をかけてコンサルタントに昇進していきます。中途採用の場合はコンサルタントやマネージャーからのキャリアスタートなど入社するファームや、それまでの経験によっても異なります。
マネージャーからの昇進にあたっては、何より成果を出し続けることが重要です。パートナーの職位までたどり着くためには実力が必要なことは間違いありません。
詳細については当社でも無料の面談を通じてご説明しています。ご興味をお持ちの方はご気軽にご相談ください。
また日本でもコンサルタントという職種の認知度が上がり、優秀な人材がそろっていると認められているため、ポストコンサルタントへの転職の選択肢も広がってきました。ポストコンサル転職の成功事例は、経営幹部などのハイクラス転職になりますが、一部の企業ではまだポストコンサルタントの受け入れに慣れていないこともあり、転職後の成功にはそれまでに培った能力を十分に発揮できる関係性の構築が重要になってきます。
転職支援の申込について
転職をご検討されていらっしゃる方は、無料で弊社コンサルタントが最新求人情報の説明や面接通過のためのアドバイスを実施しております。お気軽にご連絡ください。
メールマガジンの登録
最新の求人情報は弊社メールマガジンよりご案内をしております。
非公開求人等の新着の情報についてはメールマガジンにてご確認ください。